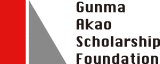Report活動レポート
ボランティア活動を通し、発展途上国の医療の現状とニーズを学ぶ
鈴木実優
群馬大学(医学部3年)
- 留学期間:
- 2024年8月24日~2024年9月21日
- 留学先:
- ケニア Mount Olives Community Health Center

今回、ケニアの田舎町(Mosocho)でのコミュニティヘルスセンターでボランティア活動を行い、多くのことを学んだ。学んだことをいくつかカテゴリーに分け、記載していく。
ケニアで多い感染症とその原因
まず初めにケニアで多い疾患についてである。事前にケニアの疾患について学習した際、マラリアや腸チフス、梅毒など性感染症を含めた感染症が多いと知ったが、現場に来るとやはり感染症は多く、感染症に感染する人だけでなく、感染症の種類の多さに驚いた。
来院してくる患者で一番多い感染症はマラリアであるが、その他にも腸チフス、赤痢アメーバ症、コレラ、そしてピロリ菌感染による消化器潰瘍などの消化器感染症や肺炎、結核の呼吸器感染症、梅毒、HIVなどの性感染症、このように多岐にわたる感染症がある。感染症蔓延の原因の主な原因は、衛生環境にあると実感した。

ケニアは国土の過半が乾燥または半乾燥地域であり、さらに雨季には安定的な国土を潤す十分な雨が降らない。また雨が降ったとしても上下水道インフラが未整備の為、適切に貯水されず、告知もなしに水道水が長時間、時には長期間に渡り断水されることも多い。
私が滞在している間も断水は1週間に2度程あり、丸一日水が出ないこともあった。そんな水資源が不足しているケニアでは、各建物の屋根に貯水槽が設置されており、溜めた雨水を生活用水として使っている。飲料水としてはとても使用できないため、ウォーターサバ―や市販のペットボトルを買うことが多い。
しかし、これらは比較的高価であり、私が滞在していた農村部では、水汲みの仕事をしている人がどこかの地下水を汲んだボトルを買う人もいる。さらに、ケニアの農村部では水洗トイレの普及はまだまだであり、多くが屋外の汲み取り式トイレである。ケニアで蔓延している感染症の多くは、水資源が不足し、上下水道インフラが未熟であることに起因していると感じた。
性感染症に対する教育や医療機関の不足・格差
一方で、性感染症に関しては、問題の根底にある教育の不足及び格差及び医療機関へのアクセスの困難さを実感した。ケニアでは、性感染症が蔓延しており、特にエイズに関しては日本の40倍の感染率であり、世界の感染率ランキングでは138位中12位と、世界と比べても依然として高い。
また、私が病院でインターンシップを行っている際もトリポネソーマが脳神経までたどり着いてしまった末期の梅毒患者や高校生の妊婦を数多く見てきた。性教育を行っている学校もあるものの性教育の質やそもそも学校にいけない子供たちが多くいること、そして経済的背景や地理的背景により医療機関に行くことのハードルが高いことが問題として考えられた。
感染症だけでなく、高血圧・肥満・糖尿病などの生活習慣病も多く、これらの背景にはよく食べ、運動をあまりしない文化背景や砂糖・米やウガリ、チャパティといった炭水化物が多い食文化がある。そして、非感染症疾患の治療は、薬物治療などの対症療法が主で、生活習慣の改善といった根本的な問題の解決には至っていない(理由として、栄養バランスの知識が不足していることに加え、栄養バランスを考えた食事をとるための十分なお金がない。たくさん食べて運動しない文化背景がある)。
ケニアの厳しい医療状況
次に、ケニアの医療状況についてである。ケニアでは保険制度は一応存在するが、ほとんど機能しておらず、保険に入っている人はほぼゼロといって過言ではない。そのため、平均月収の20,124Ksh(約2.2万円)に対する医療費は国民にとって苦しい問題であると言える。
ケニアの一人当たりの医療費の自己負担額は、20.27ドル(約2,900円)であり、Mount Olives Community Health Centerの一人当たりの平均医療費を計算すると1,821Ksh(約2,000円)であった。もちろん、外来患者と入院患者では金額に差があるが、平均2,000円の医療費は平均月収の9%を占めることが分かった。
そのため、ケニアの病院では分割払いが主流で、さらになるべく入院費がかからないよう早く帰りたいと交渉する患者も少なくない。そのため、発展途上国での医療では、経済的な問題に関しても傾聴し、寄り添っていく必要があると学んだ。
さらに、公立病院に足を運んだ際、レントゲンや保温できる保育器などもあったが、停電が頻繁に起こるケニアでは、こういった機能に優れた医療機器があっても使えないことが事実としてある。よって医療スタッフはこういった医療機器に頼らずに経験と知識、そして技術を最大限活用していた。

そして、医療機器に頼れないからこそ、患者の訴えをしっかりと聞き、自身の目、耳、手を使って診療を行っていた。ケニアではほとんどの人が英語を話せる一方で、ケニア人同士ではスワヒリ語もしくは同じ民族の場合、それぞれの言語を使って会話をし、医療の現場も例外ではない。
そのため、スワヒリ語を学ぶことこそが患者との距離、そして医療スタッフとの距離を縮める大きな一歩であると感じ、患者の訴えや気持ちを聞くためには同じ言語を話すことが必要不可欠だと考える。
ヘルスリテラシーのアンケート調査
次に、ヘルスリテラシーのアンケート調査の結果である。今回医療職員と患者もしくは家族に同じ質問用紙を用いて調査を行ったところ、驚いたことに医療職員の方が患者やその家族よりもリテラシーが低いという結果になった。
この理由としては、このアンケートは自分で自身のヘルスリテラシーを判断するものであり、医療職員はより高度な医療を知っているが故、自身との環境のギャップがあったのだと考える。
そして、医療に求めるものは?という質問に対し、患者やその家族はトイレなどの施設の向上を求める傾向が強い中、医療職員は医療機器や薬剤、職員のスキル向上を求める傾向が強かった。このアンケートを行い、医療職員の求める医療と提供できる医療の葛藤を垣間見ることができた。
アフリカの発展途上国の現状を知り、
国際機関として医療問題を解決する夢も
今回ケニアでのボランティア活動を通し、アジアの発展途上国と比べ物にならないアフリカの発展途上国の現状を身に持って知ることができた。同時に、アフリカの発展途上国の医療を向上するために自分の力だけではどうにもならない現実を痛感した。
医療職員の葛藤を知り、彼らの知識や技術では限界があり、私が考えていたよりも問題の根底は大きく、根深いものだと感じた。それでも、目の前の患者の話をよく聞き、寄り添い、その人にベストな医療を提供するしかないことも現実であり、これは、発展途上国、先進国関係ないと考える。
ケニアで医療技術も多く経験を積み、さらに言語に頼らないコミュニケーション方法を学んだ。これは、これからの大学の実習で活かしていきたい。そして将来、赤十字病院で看護技術・経験をさらに積み、より多くの医療を必要としている人の下に医療を提供できるよう国境なき医師団に入り、今回学んだ問題の背景を明らかにしていくスキル・個々の背景に寄り添った医療の提供を考える力を活かしていきたい。
そして、ケニアでの経験は私にもう一つ大きな夢を与えてくれた。それは、国際機関として医療問題を解決することである。一医療職員では、限界があることを知りもっと大きな機関で影響力を持って活動しなければならないと感じた。そのために、私はWHOに入り、世界の医療を向上することに尽力していきたい。
今回のケニアでのボランティア活動は私に多くの学びと夢を与えてくれた。そして、その機会を与えてくださったぐんま赤尾奨学財団様には多大なる感謝を申し上げます。